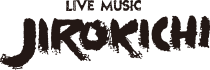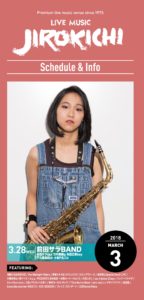毎月発行している「紙」スケジュール裏面に掲載している <店長のつぶやき>です
【2023年2月】
【2023年1月】
【2022年12月】
【2022年11月】
【2022年10月】
【2022年9月】
【2022年8月】
【2022年7月】
【2022年6月】
【2022年5月】
【2019年12月】
【2019年11月】
【2019年10月】
【2019年9月】
【2019年8月】
【2019年7月】
【2019年6月】
【2019年5月】
【2019年4月】
【2019年3月】
【2019年2月】
【2019年1月】
【2018年12月】
【2018年11月】
【2018年10月】
【2018年9月】
【2018年8月】
【2018年7月】
【2018年6月】
【2018年5月】
【2018年4月】
【2018年3月】
【2018年2月】
【2018年1月】
【2017年1月~12月】
【2016年1月~12月】
【2015年1月~12月】
【2014年1月~12月】

【2023年2月】 《三好“3吉”功郎》》
音楽を好きになったのはいつなのだろうか。
そんなことをふと考えました。
思えば、子どもの時分、お年玉でレコードを買ったり、カセットテープのダビングを貸し借りしあったりしたのは、結局、友人たちとのコミュニケーションの一環であり、特定のアーティストのレコードを集めたりしたのも、学校や部活での話題作りや、自分というキャラクターを注目させるためでしかなかった気がします。多くのプロミュージシャン・アーティストたちの回顧のように、音楽を、三度の飯より好きで好きでたまらなかった、なんてことはなく、結局、ただ、かっこをつけていただけだったのかもしれません。高校生のとき、バンドを組んだことだって同じです。文化祭に出演して女の子にモテたかっただけでした。
そんな自分が、なぜ居心地の良かった田舎のコミュニティから抜け出して、東京に出たいと思ったのか。バンドをやりたかったのかもしれませんが、今思うと、今ひとつ動機がはっきりしません。東京に住んだものの、結局、専門学校の友人たちとバンドを組むこともなく、漫然とバイトで暮らしていました。ほんとうにやりたかったら、どんな状況でもやっていたでしょうが、やりませんでした。しかし、そんなわたしが、音楽って素晴らしいと思った瞬間のことをよく覚えています。
それは三十年前。JIROKICHIにアルバイトとして入って1年くらい経ったころのことです。若かったわたしは、古いブルースしか聴かない、という馬鹿げたこだわりで自分のキャラクターを作ろうと頑張っていたらしく、ファンクや、ソウルミュージック、R&Bなどをほとんど毛嫌いしていました。ところが、深夜、酔っ払って、JIROKICHIのフロアーで半分朦朧とした意識の中、DJ役の先輩がチョイスするダンスミュージックに身を任せ、みんなと適当に踊っていたときのことです。瞬間、わたしの耳にふと入ってきたのはスライ&ザ・ファミリーストーンの「(You Caught Me )Smilin’」という曲でした。それは、わたしにある種の衝撃のようなものを与えたのです。気分よく酔って、余計なことを考えず、ただ身体を動かし、リズムに乗っていただけだったので、素直に聴けたのかもしれません。とにかく、それからというものの、わたしはスライ&ザ・ファミリーストーンをはじめ、ソウル・ミュージックが大好きになりました。
モータウンやゴスペル、ジェームス・ブラウン、ジャズなども好んで聴くようになり、そしてわたしはJIROKICHIで、熱い演奏をし、音楽で会話をする、さまざまな音楽を身につけたミュージシャンたちに憧れるようになったのでした。
要するに、わたしがほんとうに音楽に触れ、好きになったのは、JIROKICHIに入ってからだったのです。
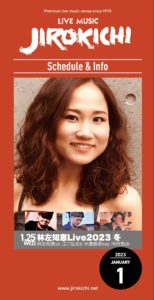
【2023年1月】 《林左知恵》》
あけましておめでとうございます。
旧年中、大変な時代を迎えてしまった中、会場にお運びいただいたお客様、配信の後売りチケットを買っていただいたお客様には、あらためて深く深く感謝いたします。ライブハウス業界の落ち込みもそろそろ底を打ったと信じて、2023年、スタッフ一同がんばっていきたいと思います。
ところで昨今、なんでも値上げ、値上げで驚いてしまいますね。とくに光熱費の請求書を見てびっくりしています。この値上げ=インフレの大きな原因は、コロナのパンデミックによるサービス業に落ち込みですが、追い討ちをかけたのがロシアのウクライナ侵攻です。せめて早く戦争が終わり、ロシア、ウクライナからの物流が以前のように戻ることを祈るばかりです。
しかし、なんでこの戦争は終わらないのか。「プーチンが侵略をやめないからだ」
そのように、ほとんどの人はきっと、ロシアが一方的に悪いのだと思ってニュースを見ているのではないでしょうか。「独裁者が隣国の領土を理不尽に奪おうとしている。助けなきゃ」
しかし、このような単純な物語を国際世論が作り出しているときは注意が必要です。
ゼレンスキーという人はほんとうにヒーローなのだろうか。プーチンは、核をちらつかせる侵略者、悪人だとマスコミに信じさせられているが、ほんとうなんだろうか。このように疑ってみることが大切です。たとえば、旧ソ連に対抗しようとして作られたヨーロッパの軍事同盟「NATO」は、かつて、旧ソ連(ロシア)にどんな約束をしていたのだろうか。ニュースを鵜呑みにせず、そういったことを調べてみる必要があるのです。極端なグローバリズムを嫌う国、ロシア・中国を面白くないと思っている勢力、巨大な国際財閥があるということ。彼らはアメリカにおいて政策に関われるような大きな力を持っているということ。そのアメリカが中心になってウクライナ支援のキャンペーンを行っているという事実。かつて、太平洋戦争でアメリカは、日本に対し、真珠湾攻撃をしかけるように仕向け、日本を侵略者、悪の国として位置付け、国際世論を作るキャンペーンをしたことはよく知られています。そしてアメリカは日本で核兵器を使い多くの人を殺したのでした。
世界は感情、宗教、マネーなど、人間の欲望が渦巻いて、極めて複雑に絡み合っています。「正義」対「悪」の戦い、などという映画のような単純な物語は存在しないのです。私たちの身の回りだって同じです。あいつとは仲良くできない、許せない、大嫌いだ。対立したあと、知恵のある人は、相手の悪口を言いふらしたりして味方を増やし、自分の立場を有利にしようと働きます。そして、相手を孤立させ、悪人であるかのように思わせるよう仕組むのです。ときにはグループを作ったり、対立の中、損得で敵味方が入れ替わったり複雑に絡み合います。しかし、私たちが、仲違いするときの様子を冷静に観察すると、ほとんどの場合、どちらが悪いとか、そういう問題ではないことに気がつきます。お互いが、いかに相手の立場や心理状態をシミュレーションできるかどうか。感情に突き動かされず、いかに状況を俯瞰して自分や相手を観察できるかどうか。このような考え方が私たちの間に広がればきっと、戦争は早く終わることでしょう。
とにかく、大変な時代ですから、みんで助け合って仲良く暮らしていきたいですね。
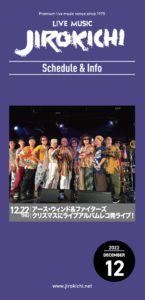
不思議なこと。
人生において、偶然にしては出来すぎていると感じるような出来ごとがしばしばあります。ずいぶん会っていないミュージシャンの噂をしていたらその人からLINEが来た、電話が来た、現れた。玄関を出ると、ふとユーミンの「ひこうき雲」が頭の中に流れ、駅前まで歩くと、駅前の路上で、若い女の子が「ひこうき雲」を歌っていた、など。
しかし、それらはすべて偶然です。人間は、ついそういった現象に、なにか特別な、暗示的なものがあるのではと錯覚する生き物です。もちろんそこには神秘的な力など働いておらず、神様からのメッセージでもなく、ほんとにたまたまなのです。なぜなら、誰かの噂をしていても、その人が現れるなんてことは、実は、ほとんどないし、しょっちゅう頭に流れる誰かの曲のメロディーを、駅前に行くと必ず路上ミュージシャンが歌っているなんてことはまずないからです。
先日、渋谷のある雑貨屋で売っていた森茉莉という作家のエッセイを買いました。
森茉莉は明治の文豪、森鴎外の娘で、エッセイスト、小説家として活躍した人です。
幻想的で優雅な世界を表現することに優れた作家で、二度、結婚しましたが、生活能力のない人だったらしく、1987年に85歳で孤独死しています。森茉莉の存在はなんとなく知っていましたが、別段興味もなく、今まで読んだことはなかったのですが、偶然手に取って、なんとなく買ったというわけです。
次のお休みの日、よく晴れていたので、先日買った森茉莉のエッセイをポケットに、三鷹駅からバスに乗って、調布の深大寺まで出かけて行きました。散歩は、非常に心地よく、名物の蕎麦を堪能し、エッセイもなかなか面白くて、とても良い休日になりました。
バスで三鷹駅に戻り、ぜんぜんお腹が空かないなぁと思いながら、夕闇の前に三鷹駅周辺を散策してみることにしました。そういえば、三鷹駅の近くに、こちらも文豪、太宰治のお墓があったことを思い出した私は、ふとお墓参りを思いつきました。スマフォを駆使し、お寺の場所を調べると、駅から歩いて12分ほどのようです。
「ここか…… 」とひとりごちながら、おおきな山門をくぐり、墓地に入って行きました。
広い墓地の一角にある太宰治の墓は、時々ファンが訪れるようで、お酒や、花などが供えられています。ここが情死したかの有名な太宰の墓か……としばし感慨にふけりました。しかし、見渡す限り墓だらけの寂しい墓地であり、他に人影もなく、不気味に静まり返っています。墓前に軽く手を合わせると、さぁもう帰ろうと振り返りました。
「えっ」
振り返った墓の墓碑名に、森林太郎と刻んであったのです。つまりそこは森鴎外の墓だったのです。
まさかと思いました。まさか、森茉莉もここに?ポケットに突っ込んだ手で文庫のエッセイを触りながら私は、背筋が寒くなるのを感じました。そうです。鴎外の墓の二つ隣にある森家の墓。ここが森茉莉のお墓だったのです。
 【2022年11月】 《リクオ with HOBO HOUSE BAND》
【2022年11月】 《リクオ with HOBO HOUSE BAND》
一乗寺フェスという京都⇆東京で繋がる配信フェスの一環で、高円寺の街を紹介するコーナーとして作成した、JIROKICHIのYouTubeチャンネルで配信中の「JIROKICHI 店長タカの高円寺のみある記」が好評です。
気軽に、台本も打ち合わせもなく、いつものようにハシゴする感じで撮影したのですが、編集が素晴らしいこともあり、なかなか面白い番組になっています。
動画を客観的に見て、あらためて思ったことがひとつありました。
それは、自分はやっぱりお酒やツマミが「好き」だということです。「飲み歩きしてるんだから当たり前じゃないか」と思われるかも知れませんが、とにかく画面に映る自分がとても楽しそうに見えたのです。とくに、各店舗のツマミ&フードを紹介するシーンなどは、わざとらしい演技もなく、静かな熱量があって、なかなかいい。自分で言うのもアレですが、なんだか、またすぐに行きたくなるような気持ちになります。
ところで、どうしてそんな熱量があったかというと、繰り返しになりますが、ほんとうにお酒やツマミが「好き」だからです。
「好き」なものを語る手つきは誰もが鮮やかで、聞くものを魅力します。その情熱は伝わるし、情熱こそが利害関係のない他者のこころを動かす唯一のチカラです。
昔は、好きだの嫌いだの言う以前に、とにかく家族を養い、飯を食って生きていかなくてはいけませんから、そういった情熱のことなど二の次、三の次だったことでしょう。わたしが子どものころだって、趣味的なものはあくまで趣味であり、道楽などと言って、それが重要だという風潮は一切ありませんでした。
現代では、若い人たちの貧困が問題になることもありますが、野垂れ死にすることはほとんどありません。情報が過剰な世の中で、みんな、自分の小さな「好き」を追求できる時代です。その中で同じ「好き」を共有するコミュニティが無数にある状況です。昔のように、みんな同じ方向を向いているわけではなく、コミュニティもさらに細部化していくことでしょう。わざわざ外に出かけなくても、都会に暮らさなくても、承認欲求を満たす手段も多く、幸福という意味で言えば、昔よりもきっと幸福な時代であることは間違いありません。
けれど、日本は、少子高齢化によって国力がおおきく落ち込んでしまいました。このままいけば、私たちの国は、裕福でない低空飛行で満足している人しかいない寂しい国になってしまうでしょう。
そんな寂しい国では、イノベーションが起きたり、新しい音楽や文化が生まれることもありません。
何が言いたいかというと、まさにこれからは「好き」をもっと追求することが大事なのではないか、ということです。そして、「好き」の熱量が半端ない人やそのコミュニティーを支援する「雰囲気」をマスコミや政府が作る。これが必要なのではないかという気がしています。なぜなら、日本にとって必要なのは世界に通用するイノベーションだからです。それも、マニアックなイノベーション。マニアックなイノベーションは、いつの時代も「好き」から生まれています。居酒屋で例えるなら、店主の「好き」が高じて提供される珍味や創作料理。なにが次代のトレンドになるかは誰にもわからないのです。
長くなりましたが、日本の生きる道は、案外そんなところにあるような気がしています。

ドン・キホーテが好きです。
と言っても、あの驚安が売りのディスカウントショップではありません。もちろん、街道沿いにあるチェーンのハンバーグ・レストランでもありません。約400年前に書かれたセルバンテスという人物の長編小説「ドン・キホーテ」のことです。有名なので皆さんよく知っているかと思いきや、史実ではなく架空の小説だということも、どんな内容であるかも知らないという人が実は多いのではないでしょうか。
中世のヨーロッパ。土地を持っている地主、郷士たちは、戦争になると自分で武具や馬を用意し、戦場に馳せ参じました。戦場で華々しく活躍し武勲を立てたものは、まさにヒーローとなり王様の娘を娶るなどして栄光をつかむこともあったようです。やがて、そういった鎧を纏った騎士たちの活躍や所作、恋の遍歴は、美化されファンタジー的な物語となって16世紀にたくさん出版されました。
そんな騎士道物語に取り憑かれたのが「ドン・キホーテ」こと、スペインはラマンチャ地方の郷士アロンソ・キハーノです。彼は土地を所有し、比較的裕福な暮らしをしていますが、暇を持て余し、読書に明け暮れていました。彼は、土地を売ってまでして騎士道小説を買い集め、朝も昼も夜も読み耽りました。騎士道小説に出てくる栄光の騎士たちの世界にどっぷりと浸かり、やがて、現実と物語の世界の区別がつかなくなったキハーノは、自分を数々の武勲を立てるはずの遍歴の騎士だと思い込むようになります。
妄想に取り憑かれた彼は、家にあった時代遅れの鎧を身につけ、槍を持ち、痩せ馬にまたがり「ドン・キホーテ・デ・ラマンチャ」と自ら名乗り、とうとう冒険の旅に出発します。しかし、正気を失った騎士の目には、何もかもが騎士道に則った冒険的出来事、ファンタジーに映ります。宿屋は立派なお城に、宿屋の親父は城主に、娘や女中は美しい姫君に、風車は巨人に。この調子でドン・キホーテは、村の小作人であるサンチョ・パンサを従え、痩せ馬ロシナンテにまたがり、各地で揉めごとや騒動を繰り返し、大怪我を負ったりしつつ、妄想に取り憑かれたまま滑稽な冒険を繰り広げて行きます。彼はまるで「ワンピース」や「ドラクエ」のような物語の世界を一人、生きているのです。
この小説は、けっこう長いのですが、サンチョ・パンサとのやりとりやエピソードが非常に面白く、当時の世相への批判、風刺が効いていて、400年前の作品とはとても思えないほどの名作です。機会があれば、ぜひ、前編だけでも読んでみて欲しい一冊です。
ところで、ずいぶん話が飛びますが、忌野清志郎さんのデビューのころのエピソードをご存知でしょうか。お母さんが高校生だった清志郎さんのことを思い悩んで、新聞の人生相談に投稿したという話です。
ギターや音楽に取り憑かれた清志郎さんは、学校にあまり行かなくなり、プロになると言って進学も諦めてしまいました。きっと親の目には、息子は頭がおかしくなってしまって妄想に憑かれてしまった……と映ったことでしょう。
つまり、なにが言いたいかというと、ロックやブルーズ、ジャズなどに取り憑かれた「ドン・キホーテ」たちが、私の周りにたくさんいる……ってことなのです。
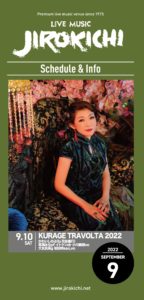
【2022年9月】 《かわいしのぶ》
バンドに誘われました。
彼らはわざわざJIROKICHIのBar Time に現れて「ギターを弾いて欲しいんです」といいます。困ったな、ギターなんてここ数年まったく触っていないし、弾けるかどうかわからないよ、と消極を表情でも伝えたのですが、彼らはまったく感じとってくれません。それどころか、高校生みたいに目をキラキラとさせて、バンドを組んでライブをするという楽しげな目的に高揚しています。わざわざ店に来てくれた上に、そんなかわいい様子を見せられたら、なんとなく無碍に断ることが難しいような感情に追い込まれ私は、とうとうバンドへの加入を承知してしまいました。
と言っても、このバンドは、あるロックイベントに15分だけ枠をもらって出演し、すぐに活動休止? するという刹那的な集まりで、イベント終了後、楽しく酒を飲めればそれでいい、という主旨のようです。15分の持ち時間といえば、おそらく二曲か三曲くらいでしょうから、そのくらいなら……と算段し了解したわけです。
私を誘いに来たのは、高円寺の焼き鳥屋の店長さんと元従業員、高円寺で評判のラーメン屋の店主でした。ほかのメンバーは、焼き肉屋さんの店主などですが、バンド名は「高円寺連合バンド」。もう少しいい名前が付いた方が良さそうですが、とにかく高円寺の飲食店店長的な人間が勢揃いして、バンドをやることになったのでした。
ところが、彼らはまったくの初心者で、楽器についてや音楽的知識は皆無。すべてを勢いだけで乗り切ろうとしています。無謀にもアレをやろう、これをやりたいと張り切っています。演奏がちゃんとできるかどうかなんて、まるっきり考えていません。果たしてどうなることやら不安でいっぱいです。けれど、普段の仕事を忘れ、みんなでリハーサルスタジオに入って、あーでもないこーでもない、とにかく、せーので音を出す、という経験のない緊張感、新鮮な気持ち、高揚を全身に顕し、みんなとても輝いて見えます。
素晴らしい。
バンドなんてそれでいい。余計なことを考えない勢いこそがもっとも魅力的で大事だったのです。プロミュージシャンたちはそういうわけにはいかないかも知れませんけれど、音を間違えるとかテンポが合わないとか、そんなことどうでも良くって、みんなで集まって一緒に音を出すという楽しさ。私は長く業界にいて、すっかり熟れてしまい、そういった初心を忘れていたのでした。

【2022年8月】 《加藤エレナ&江口弘史 DUO》
新型コロナウイルス第七波の蔓延が広がっています。(7/23現在)一日で、35,000人というとんでもない勢いです。とはいえ、弱毒化していることは間違いなさそうで、このまま、単なる風邪という認識が世間に受け入れられるようになることを願うばかりです。
新型コロナウイルスの存在が私たちの耳目に届き始めたのは、2019年の暮れでした。JIROKICIHIは、45周年のイベントが目前で、てんやわんやしているころだったと記憶しています。そのころはまだ、中国で発生したウイルスがまさか世界中に広がって……などと想像もしていませんでした。
年が明け、二月に入って、45周年イベントはスタートしましたが、日本でも、じわじわと感染者が出始め、亡くなる人も出てきました。JIROKICHIはスペシャルライブ月間の途中に差し掛かり、なんとか無事に最後まで終えたいと思っていました。報道が加熱し、世間の話題はコロナ一色という感じになってきましたが、それでも、イベントが中止になるほどのことではないという認識でした。ですから、海外から招く予定だったアーティストの来日が危うくなり、リハーサルまで済ませていた山下達郎さんのライブが延期・中止になりそうだという話が出たときは、まさか、という思いでした。確かにウイルスの危険性が世間に知られ始め、今のうちに食い止めなければならないという論調が主になりつつありましたが、感染者はまだ二桁くらいで、周囲にはまったく感染者が現れるような気配もなく、現実だとはとても思えなかったのです。
結局、山下達郎さんのライブなど、いくつかの日程が延期、中止、ということになり、本来なら打ち上げで、スタッフ一同「45周年、おつかれさま!」となるところが、最終日、終わったら即解散みたいな雰囲気になってしまい、皆、押し黙って、暗い気持ちで、淡々と片付けをしたことを思い出します。
その後、休業要請があり、家からも出られない、長く辛い自粛の日々が始まります。
そしてようやく今年の春をもって、通常に……と思った矢先、またこの第七波。おそらく、このあとも、第八波、九波と繰り返すのでしょうが、そうこうしているうちに、JIROKICHIは、50周年ということになってしまいそうです。
50周年は果たして無事に迎えられるのでしょうか。
いや、大丈夫です。音楽が人々を興奮させるコンテンツである限り、ライブハウスの存在は重要だと考えているからです。そう思い続けている限り、私たちは、日々、素晴らしいミュージシャンたちとともに、質の高いライブをお届けしたいと考えています。

【2022年7月】 《小野塚晃トリオ》
ヒトは、退屈を我慢できません。退屈を感じると、スマフォをいじったり、テレビをつけたりYouTubeを観たり、どこかに出かけたりと退屈な時間を埋めるために様々な行動をおこします。
けれど、退屈=暇、ではないので厄介です。ひまつぶしになにかをやっても退屈なものは退屈です。予定が埋まっていていろいろ忙しいのに、退屈を感じることがあるのは、皆さんも経験があるのではないでしょうか。
好きなミュージシャンのライブを聴いているのに、ふと退屈を感じる瞬間がある。ようやく休みをとって旅行に出かけたのに、退屈を感じる時間がある。デートしているのに退屈で持て余すことがある……など。楽しいことをしているんだし退屈なはずはないのに……なぜか退屈している自分がいる。
では、私たちは、退屈だからと行動を起こすとき、ほんとうはなにを求めているのでしょうか。
昔、王様や殿様は、馬に乗り、家来を引き連れて、ウサギ狩りや鷹狩りなどに興じました。もちろんウサギ狩りはウサギを捕らえるのが目的です。しかし、狩りに出る前に獲物のウサギを差し出されても、ちっとも嬉しくない。なにが言いたいかというと、ウサギ狩りは、ウサギそれ自体が目的ではないということです。狩りのテクニックを駆使して競い合いあったり、その成果を周囲に誇って賞賛されたりする……つまり、「狩り」というゲーム、そのプレイにおいて興奮する、脳内にアドレナリンを放出する、それが目的なのです。
退屈を埋めて満足するためには、興奮させてくれるナニかが必要なのだとわかりました。スリルを味わったり、どきどきする恋愛をしたり、すごく美味しい物を食べたり。ときには興奮させるそれが恐ろしいニュースだったり、下世話なスキャンダルだったりすることもあります。電話でクレームをつけたり、喧嘩をしたり、つまり、「怒り」という感情も興奮と直結しています。興奮という現象のスイッチに善悪の区別はないのです。
ライブハウスでライブを楽しむことも退屈を埋めてくれる時間です。しかし、つまらないライブだとちっとも興奮しませんよね。けれど素晴らしい演奏をしているミュージシャンの興奮が伝わってくるとき……私たちは次第に空気に感化されていきます。
そして、次第にこっちも興奮してくる。
いいライブとは、わたしたちを興奮させてくれるライブのことだったんですね。

ニューオリンズ在住のミュージシャン・山岸潤史さんは、

蔓延防止期間も終わり、ようやく通常のスケジュールでライブが組めるようになってきました。未曾有のウイルス蔓延に三年以上沈んだ世界各国ですが、街を歩くと活気を感じるようにもなり、ようやく長いトンネルの出口が日本にも見えてきたような気がしています。
ところで、最悪だったコロナ禍。まだ不況本番はこれからという感じですが、JIROKICHIはかなりのピンチに陥りました。
しかし、休業を余儀なくされた中、ピンチはチャンスということで、スタッフ一丸となって取り組んで成果を上げたことがいくつかあります。その一つがライブのYouTube生配信です。
ライブの配信なんて考えたこともなく、はっきり言って闇雲でした。どうしたらいいかぜんぜんわかりませんし、休業しているので、機材を買う現金も店にありません。しかし、ミュージシャンの皆様や、お客様の支援で、なんとか最低限の機材を買うことができ、スタッフのスマフォをかき集め、カメラとして使いつつ、日々研究し、ミュージシャンたちの協力も得てなんとか配信を軌道に乗せることができました。お陰様で、今では楽しみにしている方も大勢いて、大変ご好評をいただいているようです。
毎日、配信ライブをしていて、気がついたことが一つあります。
話は逸れますが、ある日、野球中継を観ていると、コントロールも良く速い球を投げているエース級の投手が、開始早々連続ヒットを打たれ得点を許してしまいました。元投手の解説者は、「今日は投げるボールに魂が入っていないですね」というようなことを言っていました。だからいくら早くてもバットの芯で捉えられてしまうと。
カメラなんか意識せず、コロナ以前のように普通にやろうというミュージシャンもいます。
みなさんプロミュージシャンだし、会場では、迫力のあるいつも通りのいい演奏をしています。しかし、あとで配信の映像を観ると、カメラの向こうを意識していないと思われるライブは、なぜか良くないのです。配信ライブでは演奏の良さは伝わらない、と思っている人もいるかもしれません。けれど、ミュージシャンがカメラの向こう側の世界を意識し、魂を込めた演奏をすると、必ず視聴者に伝わるのです。
ネット上では、しばしば怪しい、非科学的な陰謀説を流布して、閲覧者の不安を煽り、アクセス数をアップさせているような人がいます。そういった説を真に受け、正義感に駆られ、悪気なく、本気でそう思ってリンクを貼ってしまったり、リツイートしたりしてバズるのに積極的に加担している人も多いようです。
この度の新型コロナウィルスの感染拡大についても、中国が開発したウィルス兵器だとか、東日本の震災なども他国の地震兵器であるとか、安倍首相のスキャンダルが持ち上がるたびに、タイミング良く芸能人の薬物逮捕があるなど、見えない大きな権力が、一般庶民の支配のために、あるいは人口調整などのために、陰謀を企画して実行していると本気で信じてる人がかなり多いようです。
けれど、歴史を学んだり、行動経済についてちょっと勉強したりするとわかるのですが、国家、もしくは黒幕的な人物が、もしなんらかの陰謀を実行するとしたら、相当な経費と労力がかかると予想できます。だいたいにおいて、そのような兵器を使用する場合、精度を上げるために実験を繰り返すことになるでしょうから、その間の機密漏洩に関する防止策だけでも相当な労力と予算を当てなければならないでしょう。ですから、よほどの信念、徹底した組織力、組織の人間が有意義であると納得しうるほどの社会的な価値、理由、そして大国に匹敵する国家予算規模の資金力がないと実行できないはずです。
子供のころよく見たヒーローもの、仮面ライダーなどでは、ショッカーという世界中に支部を持つ秘密組織が、日々、犯罪や、破壊工作を行なっています。けれど、よく考えると、あのような組織を維持するためには、莫大な資金が必要です。アンデス山脈の秘密のアジトに住むという首領が、資金を調達し、すべて自己負担しているのでしょうが、ということは、首領は、クラウドファンディングなどなんらかの経済活動を行なって資金を集めていると考えられます。ですから、破壊工作や犯罪を蔓延させて、社会情勢を悪化させ、人々を不安にすればするほど、経済活動は麻痺し、資金獲得において不利になるわけですから、そこには大きなジレンマが生まれるはずです。
ある特定の国家や、見えない闇の支配者が、征服や、世界の人口調節を目的としてなにか行動を起こすなら、どのように広がるか予測の困難である危険なウィルスを蔓延させたり、国家予算に匹敵するような金を投入して、どれほどの規模の被害をもたらすか予測できない地震兵器で他国を攻撃したりすることは、選択肢として上策とは言えないでしょう。その必要が本当にあれぼ、例えば、中国の一人っ子政策のように、きちんと法律に則って、低コストで効率のいいやり方を考えるはずです。洗脳についても、例えば国民全てにマイクロチップを埋め込むなどを実行するとすれば、手術費用など巨額な予算を当てなければなりませんし、そもそも国民から大きな反発が予想されます。では、秘密裏に行うとしてもプロジェクトが大きすぎて、関わる人が多く、漏洩のリスクが大きすぎます。
昔、米ソの冷戦時代、アメリカが実際に行った「MKサーチ」と呼ばれる洗脳実験の話があります。敵国の重要人物などを想定し、機密事項を自白させたり、あるいは洗脳後に本国に帰し、ここぞというタイミングで裏切らせるというようなことが可能かどうかの実験です。米国は、この事件を国家プロジェクトとして、相当な予算を投入して行っていたそうです。
様々な実験が行われたそうですが、ある科学者が開発した薬物を投与した結果、一定の効果が認められたことがありました。売春婦を使ったその事件で、薬を投与された男が、機密事項をベラベラ喋ったのです。有効との判断で、薬物は大量に作れられましたが、実験を繰り返すうちに、投与された人物がどのような状態になるか正確な予測ができず、やはり洗脳は難しく兵器として使用することは不可能という結論になったそうです。結局、プロジェクトは放棄されてしまいました。そして、残ったのは、大量に生産された薬物です。軍の倉庫に保管され、廃棄される予定でしたが、関係者が横流しをし、米国に大量に流通することになりました。そうです。それが、あの伝説のウッドストックに象徴される、ヒッピームーブメントを形成する動力になったLSDという合成麻薬でした。
 【2020年2月】 JIROKICHI 45th Anniversary [LIVE MUSIC LIVES ON]
【2020年2月】 JIROKICHI 45th Anniversary [LIVE MUSIC LIVES ON]
※スタッフのつぶやきはお休み
 【2020年1月】 《令和2年度も奇数月には逢いましょう」-大西ユカリの長生きこそがロックンロールだ-》
【2020年1月】 《令和2年度も奇数月には逢いましょう」-大西ユカリの長生きこそがロックンロールだ-》
※スタッフのつぶやきはお休み
 【2019年12月】 《HENRY DOMENICO DURANTE(ヘンリー・ドメニコ・デュランテ)STELLA ALA LUCE PONTORIERO(ステッラ・アラ・ルチェ・ポントリエロ)pf》
【2019年12月】 《HENRY DOMENICO DURANTE(ヘンリー・ドメニコ・デュランテ)STELLA ALA LUCE PONTORIERO(ステッラ・アラ・ルチェ・ポントリエロ)pf》
※スタッフのつぶやきはお休み
JIROKICHIは、お陰様で来年45周年を迎えることになりました。これも偏に、日々出演してくれるミュージシャンの方々と、ご来場くださるお客様のおかげです。いつも本当にありがとうございます。つきましては、2020年2/1~3/18の期間、日替わりのスペシャルライブを行うことになりました。皆様、11月半ばには超豪華な顔ぶれが発表されますので、お楽しみになさっていてください。
ところで、関東を直撃した台風19号、すごかったですね。幸い、高円寺はそれほど被害はなくて、また、店も浸水などせずに済みましたが、温暖化の影響かどうか、毎年、こんなふうに大きな台風がやってくるようだとたまりませんね。もう25年以上前のことですが、今回のように大きな台風がきて、大雨が降ったときのことです。まさかJIROKICHIのビル、壁から水が染み出して浸水してくるなんて誰も思っていなかったので、特に対策もせず、機材やレコード、その他ビデオテープなどもそのままだったわけです。翌日のライブは、たしか、ホトケさんや山岸さんたちのセッションで、台風一過の午後、スタッフが店に来てみると、床は一面水浸し。いや、もう、浅い池のようになっていたわけです。当然ライブは中止になり、その日の出演ミュージシャンたちも手伝ってくれて、なんとか水をかき出したのですが、床に置いてあったものはすべて水に浸かってしまったために、冷蔵庫は壊れるし、貴重なビデオテープやレコード、カセットテープ、予備の機材などほとんどダメになってしまいました。ようやく水が引いて店内が乾くと、床の板もボロボロになってしまい、結局全部張り替えなければならなくなりました。その後も度々浸水の被害に遭ったため、大雨が降ると、機材などは高いところにあげて帰るようにしていますが、今回のような台風が来たり、大雨が続いたりすると、私たちは、いつもいつもヒヤヒヤさせられるのです。
思い起こせば浸水もそうですが、とにかく、いろんなことがあって大変な45年でした。けれど、どうにかここまでやってこれました。2011年の震災のピンチも、マスター荒井誠の急逝も乗り越え、なんとかやってきたのです。お客様とミュージシャンの方々には感謝しかありません。ほんとうに、ほんとうに、いつもありがとうございます。そして、今後とも、JIROKICHIをどうかよろしくお願いします。
最近は、遺伝学がかなり発展していて、進化学や脳科学、認知心理学などと絡めて、私たち人間の能力について、かなりのことが明らかになっています。昔は、有名人の誰々の子育て法とか、英才教育とか、幼い頃の家庭環境が大切であると私たちは思っていました。たしかに音楽においては、5歳頃までに音感を身につけるかどうかで、将来、大きな差が生まれるということは、ライブハウスという現場にいて、また、自分のバンド活動の体験からもよくわかります。きっと、JIROKICHIに出演する一流ミュージシャンたちのほとんどは、早くからなんらかの音楽教育を受けているはずです。
しかし、英才教育や、有名私立校に入学させるなど、子供の教育に投資し、環境を整えてあげることについては、実は、ほとんど意味がないのだそうです。とくに音楽や絵画、文章を書くことなど芸術的才能に関しては、遺伝によるところがほとんどで、才能のない人にいくら教育をほどこしても、本人が頑張ればある程度まではできるにしても、結局はものにならないらしいのです。とはいっても、遺伝というのは複雑で、生まれた国とか、生活環境に左右されることだってないとは言えないません。けれど、勘違いされやすいので慎重に論じられるべきですが、生涯所得や、性格、犯罪率の高さなども遺伝によるところが大きいらしく、これまで私たちが受けた画一的な教育というものは、見直される時期に来ているのかもしれません。アンジェリーナ・ジョリーというアメリカの有名女優は、遺伝子検査を受け、乳癌と卵巣癌になる確率が非常に高いという結果を受け取り、驚くべきことに、健康な乳房(乳腺)と卵巣を切除してしまいました。信じられないような行動……と思うひともいるかもしれませんが、近未来においては、きっと当たり前の予防治療となることでしょう。
では、遠くない将来、天才とか、遺伝的に優れた人を選別して、それ以外を淘汰させるような政策を取る時代になったりするのでしょうか。いえ、どうやら、そうはならないようです。例えば、古代なら生かされた遺伝的身体能力も現代においてはあまり役に立たないとか、高度な知識を必要とするIT社会で有利な遺伝的知能も、AI(人工知能)が中心となる未来の世界ではほとんど役に立たなくなるということだってあるかもしれません。普段、職場でバカにされているような人が、実は遺伝的に優れた臭覚を持っていて、そういう人がもっとも必要とされる時代だってくるかもしれないのです。
つまり、私たち人類の淘汰されなかった多様性は、人類が繁栄するために必要だったということです。かつてヒットラーがとった政策のように、優れているとされる遺伝子ばかりを選んで積極的に交配させる、などという行いは、逆に人類を滅亡に導くかもしれません。
音楽的に才能のある遺伝子を持って生まれた人は、それを生かし、人々を楽しませればいい。頭の良い人は、それを生かし、社会の発展に貢献すればいい。一般の凡庸な人だって、職場やチーム、バンド、遊び仲間など、現場、場面において、例えばいじられ役とか、和ませ役とか、そういう遺伝的才能を発揮して、周囲を楽しく明るくしたりしている人だっているのです。要するに、遺伝的才能なんてどう転ぶかわからないのだし、あまり気にすることはないのかもしれません。
若い頃は、名前が出てこないとか、なかなか顔を憶えられないなどという大人たちの感覚がまったく理解できませんでした。小中高時代の学友や、先生の名前、近所の人の名前などもすぐに思い出せたものです。ところが、徐々に記憶能力は衰え、最近では、好きだったバンド名や、曲名、ミュージシャンの名前なども出てこなくなって、会話がスムーズに繋がらないという場面も増え、この先どうなってしまうのかと、思わず自身を憂いてしまう今日この頃です。新たな情報を毎日のようにインプットするわけですから、脳の許容量ということもあるだろうし、仕方がないとは思いますが、せっかく読んだ本の内容を忘れてしまったり、憶えておきたかった場面や面白い話などを忘れてしまうのは悲しいですよね。
最近読んだ脳科学の本によると、右利きの人は、右手に何かを持って強く握りながら憶えるようにすると、記憶力がかなりアップするそうです。反対に、思い出すときは左手を強く握るのだそうです。左利きの人は、多分逆だということでしょうが、これはまだ実験のデータがないとのこと。皆さん、忘れなかったら、是非試してみてください。
最近、ミュージシャンの方々と、ライブ終了後のカウンターで話をしていて、なかなかおもしろかった話題を忘れないうちに書き留めておこうと思います。皆さん、コンダラという道具をご存知でしょうか。昔、「巨人の星」というスポ根テレビアニメがありましたが、あのオープニングテーマに出てくる道具です。「重いコンダラ、試練の道を~♫」はい、主人公、星飛雄馬がグランドで懸命に引いている、あの大きくて重いグランド整備用のローラーのことですね。もうお気づきだと思いますが、変ですよね。何を言っているんだ、「思い込んだら試練の道を~」だろ、と。
昔、あるベーシストが、自分の所属するバンドの某ギタリストに「知ってる? あれ、コンダラっていう道具なんだよ」とウソを教えたところ、彼はそれをずっと信じていたんだそうです。最近、その話がデタラメだと知ったギタリストは「騙された〜」と、憤慨したそうですが、これ、もしかしたら、意外と勘違いしていた人も多いんじゃないか、という話になりました。さっそくググってみると、これ、相当な数の方が「重いコンダラ」と思い込んでいたようです。コンダラと言えば話が通じる、というくらいだったのです。驚きました。後日、日本語の誤用にうるさいある著者の本がこのことを面白おかしく取り上げていて、「重いコンダラ、試練の道を♫」の方が、詩的に素晴らしいじゃないかと書いていて、うんなるほど、と思いました。
 【2019年8月】 《中川敬×リクオ》
【2019年8月】 《中川敬×リクオ》
音楽は、抑揚をつけて言葉を唱えることや、感情のほとばしりによる発声、それに伴う手拍子や、猛獣の撃退に使った鐘、法螺貝、太鼓に似た道具類などを使うようになったことによって、次第に形作られていったそうです。やがてそういった最初期の「音楽」は、儀式や、儀礼、祭事などで必須のものとなり、琴や笛などが用いられ、糸を張って音を出す楽器から音階やハーモニーが発見され、長い年月を経て、次第に娯楽的なものになっていったと考えられています。音楽を理解できるのは人間だけだと言われています。遺伝的に近いヒト以外の霊長類はビート(拍子)やテンポに反応できないのだそうです。人類は、言葉をツールとして使うようになり、それに伴って脳を進化させてきました。その進化の過程で、音楽に対する能力を獲得していったようです。
ところで、音階の発見ってすごいですよね。いわゆる「ド」の音から、オクターブ高い「ド」までの音の高低を、12音で区切って私たちは今日、音楽において使っています。どうしてオクターブ内で音を区切るかというと、ヒトに共通する感覚として、ある音の2倍の周波数を、高いけれど同じ音と認識できるからです。ですから、実はオクターブ内をどう区切ってもいいのですが、現在、ほとんどの楽曲で使われているのは、12音で区切った音階(12平均律)です。どうしてかというと、音楽を作ったり演奏したりする上で一番便利だからです。本当は、周波数的に、和音がもっと美しく響く音律がいくつかあるのですが、転調させるとたちまち不協和になってしまったり、オクターブ高いドの音が微妙にずれていってしまったりするのです。
平均律12音階のうちの7つの音であるドレミファソラシドが、いわゆる基本の音階として私たちがよく知っている音の並びです。弾いてみます。子どもの頃から慣れ親しんでいるあの音階です。次に、ミとラとシを半音下げてドから弾いてみます、するとなぜか悲しい感じの響きになります。こうして様々な音階が生まれ、情緒がある響きとか、緊張感を感じさせる音階とか、様々な音の並びが知られています。そしてその音階上には、ドからレを飛ばしてド、ミ、ソと同時に鳴らすと、和音という協和の響きがあることが発見され、起結感のあるメロディーに和音をつけると、コード進行という規則性があることもわかりました。
さて、12音階を平均律で区切ることが、和音に多少の不協和があっても、便利であることには納得がいきましたが、もっと細分化してみるとどうなるのでしょうか。例えばドとレ♭の間にもう一音入れたような音階です。微分音というそうです。微分音を使って新しい音楽は作れないのでしょうか。ググってみると、24音階にチューニングされたエレピで演奏してみました、という映像を発見。うーんやっぱりチューニングが狂っているふうにしか……と思って聴いていましたが、よく考えると、ブルースの演奏で用いられるスライド・ギターの、弦を滑らす音に似ていることに気がつきました。なるほど、やっぱりそうなるか。

【2019年7月】 《sorano》
正義という概念。実はこれ、かなり厄介なものですよね。「誰か」が現状に不満を覚え「正義」に駆られた結果、暴動が起きたり、戦争が起きたりしているのです。戦争が起きれば、街は荒廃し、多くの人々が犠牲になります。難民が生まれ、子供たちが貧困に苦しむ不平等な世界になってしまいます。
ところで「正義」がどうして不幸を招くのでしょうか。正義といえば、正義の味方とか、悪を懲らしめるスーパーヒーローなどを思い浮かべるし、正義感の強い人とか、正義の為に戦うとか、なんだか立派な概念のような気がします。けれど正義の定義は性別や人種によって違ったりもする曖昧なもののような気もします。「正義」って一体何なのでしょうか。正義は相対的なもので、悪と対峙します。「悪」は悪いことだから、みんなが悪いと共通認識している犯罪や、不正を裁き、正すのが正義と言えそうです。けれどイエス・キリストの言った言葉や、ムハンマドの残した言葉を厳格に守るのも正義だし、両親や、国家が定めたその国特有の法律や、特定のグループ内(暴力組織だとしても)で決められているルールを守ることも正義かもしれません。経済学の概念に、トレードオフという考え方があります。たとえば、Aさんが100円を握りしめ、果物屋さんに買い物に出かけたとします。店頭にはリンゴとオレンジが並んで置いてあります。それぞれ一個100円です。Aさんはリンゴもオレンジも両方欲しいと思っていますが、100円しか持っていないので、どちらか一個しか買えません。普通ならあきらめてどちらかを買うことになりますよね。しかし、この買い物に「正義」(もしくは宗教)というエッセンスを与えるとどうなるでしょうか。1.リンゴもオレンジも両方とも味わいたいのにどうして私はリンゴしか買えないのだろう(神さまが約束してくださったのに)→2.リンゴもオレンジも100円で買えるユートピアがどこかにあるはずだ→3.オレンジとリンゴを100円で売ってくれない果物屋は悪い店だ、強欲でけしからん……。
このように思考が変化していくのだそうです。結果、果物屋の店主を罵倒するとか、最悪の場合、打ちこわして略奪……つまり戦争が起きるというわけです。正義なんてウソでした。けれど戦争なんかあってはなりません。そこで、頭のいい人は、戦争の起きない理論もちゃんと提示しています。果物屋さんにはBさんも連れていくのです。Bさんも100円だけ持っていて、両方食べたいと思っています。どうするか。Aさんはリンゴを買います。Bさんはオレンジを買うのです。持って帰って、家で半分に切って分ければ、二人とも両方味わえるというわけです。本当は二人ともリンゴもオレンジも丸々一個食べたいところですが、それは両方味わえたのだから良しとして我慢します。この考え方を人々が応用すれば戦争は起きないというわけです。この超簡単な論理を世界人口の半分くらいが理解していれば、戦争も貧困もなくなるそうです。でも現実は……。とにかく、ギターをかき鳴らして「戦争反対」と叫んでいるだけではダメみたいですね。
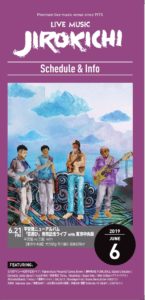
【2019年6月】 《平安隆 with 東京中央線》
昔、アニメ化もされて流行った漫画に、「美味しんぼ」という作品があります。今は確か休載中だったと思いますが、100巻を超える長い連載を誇るグルメ漫画です。山岡士郎と栗田ゆう子という新聞記者が、当代随一の芸術家で美食家である海原雄山という豪傑と、料理で対決をする話を軸に、当時の底の浅いグルメ文化を批判し、食で人を感動させ、様々な問題を解決していく人間ドラマです。
最近、あらためて、アニメの方を観ていて気がついたことがあります。主人公、山岡士郎と栗田ゆう子の二人が、ある有名評論家のところへ記事の執筆依頼に行くと、昨今のグルメブームとやらに嫌気がさして食べ物について書くことはやめたと、断られてしまいます。士郎は一計を案じ、有名評論家を禅寺に連れて行き、洗練された胡麻豆腐を食べさせ、感動をさせることに成功します。結果、仕事の依頼を承知してもらえるのですが、気になったのはその内容ではなく、背景に描かれていた、当時の日本の風潮です。
1980年代、日本は世界一豊かになり、お金持ちは海外旅行に行って爆買い。パリなどで高級ブランド品を買いあさり、高級レストランで高級な料理を食べまくります。アニメを観ていて、ああ、そういえばそういう時代だったな、と思ったと同時に、これ、つい最近まで中国人たちが日本で見せていた爆買いの姿と同じじゃないか……と気がつきました。かつて、日本人もお金持ちになって、そのような行動をして、海外で顰蹙をかっていたのです。しかし、急に豊かになったりすれば、そういう風になるのもしかたがないのかもしれません。古代、ヨーロッパの大部分を版図に収め、大繁栄したローマ帝国は、従えた各地域から奴隷を連れて来て働かせたため、豊かになって、ローマ人たちは毎晩のように朝から晩まで酒池肉林の宴会三昧だったそうです。地方の名産品を買い集め、贅沢な料理を食べまくり、お腹がいっぱいになると、医者が特別に調合した吐き薬を飲んで全部吐き出し、また、贅沢な料理を運ばせていたそうです。しかし、その栄華を極めたローマも東西に分裂し、西ローマ帝国は、ゲルマン人たちの流入によって混乱し、滅びてしまいました。 日本は、少子高齢化という構造的な問題を抱え、中国は、アメリカとの貿易戦争に突入し、ともに斜陽の時代を迎えています。両国とも、まだ滅びないとは思いますが、これ以上、豊かになることはないかもしれません。しかし、これからは、物質的な豊かさを追求するのではなく、心の豊かさを追求する時代になるはずです。音楽も、豊かな人生のツールの一つとして、残っていくでしょうから、ライブハウスもまだ必要とされるでしょう。というわけで、来年の令和二年、JIROKICHIは45周年を迎えます。スタッフ一同、頑張って行きたいと思います。
令和。なかなかいい元号だと思いますが、「学者連中の知識を疑うよ。本当はレイワじゃなくて、リョウワと読ませるべきだ……」と興奮気味におっしゃっていたベーシストの方がいました。実際のところはどうなんでしょうね。ともあれ、新しい時代がスタートします。令和の時代、日本は大きく変貌することでしょう。資本主義の社会は、経済成長を続けなければいけないという宿命にあるのですが、中国や、東南アジア諸国の成長に比べ、日本の経済は失速してしまいました。ところで、経済活動の原動力といえば「欲望」です。人々に欲望があるからこそ経済が回るのです。欲望などというと、欲望丸出し、強欲、欲張りなど、その言葉にはよくないイメージがありますが、例えば、お金が欲しいと思うから働くのだし、もっと稼ぎたいと思って会社を起こしたり、投資したり、アイデアをひねったり、勉強をしたりするのです。日本は少子高齢化によって、欲望の強い若い年代の人たちが大きく減ってしまいました。輪をかけて、インターネットの普及により、安価な娯楽を享受できるようになり、購買意欲も後退しました。そうなると、働き手も、消費者も少ないという社会になるわけですから、税収も減るし、国力は衰える一方です。安倍さんのその場しのぎの政策は、今はうまく行っているように見えますが、将来の日本人に大きな負の財産を残すことになりました。国が抱えている莫大な借金がさらに増えたのです。今の子供たちが働き盛りになるころには、年金制度も、税制も、今の状態を保っていられないでしょう。そうなると、今の日本が維持されるためには、移民を受け入れるしかありません。海外から若い労働力と消費者を呼びこまなければならないのです。しかし、日本人は、島国で、鎖国状態が長かった時代があったせいか、異国の人を受け入れるのに抵抗がある人々です。例えば、外国人の犯罪などに過剰に反応します。ですから、急激に異国の顔だらけの国になるということはないでしょうが、混血も進むだろうし、数十年後には、いわゆる日本人的な顔の人は、きっと少なくなっていることでしょう。ライブハウスや、音楽産業の形態も変わって、例えば、東南アジア系の二世バンドとかが、日本で新らしい音楽を産んで、一時代を作ったりするかもしれません。
まあ、とにかく令和。平成のように、戦争のない時代であることを心から願います。
 【2019年4月】 《Enzo Favata Crossing Quartet》
【2019年4月】 《Enzo Favata Crossing Quartet》
イタリアのベテランサックスプレイヤー、エンツォ・ファヴァータさんという方が、自身のグループを率いて来日し、ジロキチで二日間演奏してくれることになりました。(4/10、11=エンツォ・ファヴァータ・クロッシング・カルテット)エンツォ・ファヴァータさんは、長年に渡り、ジャズや世界各地の民族的要素をミックスした音楽を追求してきた、ヨーロッパでは著名な方だそうで、サックスだけではなく、バンドネオンなども演奏する多才な人のようです。映像を見ましたが、喉の奥にまで届いて響くような、素晴らしい演奏が間近で聴けそうで、今からとても楽しみにしています。ところで、エンツォ・ファヴァータさんは、イタリアという国を構成する大きな島の一つ、サルデーニャ島という島のご出身だそうです。イタリアといえば、マフィアで有名なシチリア島は知っていましたが、サルデーニャという島は初めて聞いたので、さっそく調べてみることにしました。
サルデーニャはシチリア島とほぼ同じくらいの大きい島で、東京都の10倍くらいあるそうです。ちなみに地図で見ると、すぐ上に、あのナポレオンの生まれた島、フランス領コルシカ島があります。古代より、地中海を渡る上で、ヨーロッパとアフリカをつなぐ中継地点として重要な島だったそうです。王国として独立していた時期があったり、オーストリア領やスペイン領になったりと、複雑で入り組んだ歴史を持っています。現在はイタリア領なので、イタリア語が公用語ですが、先史時代のヨーロッパ人の貴重な遺伝子を残すというサルデーニャ人が住み、サルデーニャ語が広く使われています。とにかく天国かと思うほど美しい島だそうです。
当日は、サルデーニャのワインやチーズなどを仕入れて、来てくれた方に提供したいと思い、ついでに料理についても調べてみることにしました。サルデーニャの料理は、基本、イタリア料理なのですが、北アフリアやアラブの影響も受けて独自に発展しました。豊富な魚介類を使った料理や、羊の肉の肉料理、パスタ、薄く焼いた硬いパンなどを食べるようです。当日、勉強して、なにかサルデーニャ料理を1品作ろうかとも思いましたが、羊の丸焼きの画像がドーンと出てきて、あ、こりゃだめだ……とあっさりあきらめました。ところで、仕入れようと思っているチーズは、ペコリーノという羊の硬いチーズで、もともと保存用に作ったため、けっこう塩分が強いとか。サルデーニャ産のワインも飲んだことがないので楽しみです。
ちなみにイワシのことを英語でサーディンと言いますが、サーディンはこの島の名前が由来なのだそうです。へー。
「平成」が終わります。「昭和」は歴代最長の62年(実質)という長きに渡って続きましたが、「平成」は31年でお了いということになりました。古代から数え、247もある元号の平均年数は、だいたい5年くらいだそうですから、「平成」もかなり長かったほうなのだそうです。次の元号は、一体どの漢字が選ばれるのでしょうか。選定はかなり難しいそうです。かつて元号を使っていたシナ(中国)などと重複してはいけないし、その歴代帝王の諡号(死んでから付けられるおくり名)や、宮殿、土地名なども使えません。しかも選ばれた言葉の意義は深長なものでなければいけないそうです。さらに「論語」「孟子」など、中国の古典から引用すること、音階調和的にも優れ、簡単平易なものと定められているようなので、依頼され、案を提出する学者の方々は、すごく頭を悩ませることでしょう。明治はM、大正はT、昭和はS、平成はH、この並びのアルファベットともかぶってはいけないそうですから、過去の没案を持ってきたりして検討するほうが早いのではないでしょうか。ところで元号というのは、中国の影響下にあったアジア東部の国々で使われた紀年法の一種で、特定の年代につけられる称号です。前漢の武帝のころ(紀元前115年)に創始され、かつては、朝鮮、ベトナムでも使用されていましたが、現在は日本だけが採用しているシステムです。日本が元号を定めて使うようになったのは、飛鳥時代、西暦でいうと645年の「大化」からとされています。歴史の授業でならうあの有名な「大化の改新」の「大化」ですね。現在は、天皇の崩御、譲位があったときのみ改元されることになっていますが、「明治」以前は、災害や戦乱、社会不安など、いろいろな理由でしょっちゅう改元していました。飛鳥時代は面白くて、白いキジを献上されたから「白雉」とか、甲羅に良い文字が浮いて出たカメをもらったから「霊亀」とか、金を献上されてめでたいから「大宝」とか。ちなみに、明治天皇の父親、孝明天皇の時代は6回も改元しています。黒船来航、桜田門外の変など、幕末は、国を揺るがす大事件がたくさんあったので、皇室も幕府も、改元によって悪い流れを変えたいという願いがあったんでしょうね。
 【2019年2月】 《アース・ウインド&ファイターズ》
【2019年2月】 《アース・ウインド&ファイターズ》
30年前、アース・ウインド&ファイヤーのコピーをやりたいとメンバーを集め、大阪で「アース・ウインド&ファイターズ」を結成した、ボーカルの橋本仁さんは、まだライブをやるかどうかも決まっていない最初のリハーサルで、すでにカツラをかぶり、衣装を着け、モーリス・ホワイトのいでたちで現れたそうです。 やっぱり有名になる人というのは、最初から気合が違いますね。
ところで、モーリス・ホワイトの髪型を再現するためには、まずハゲヅラをかぶり、その上から、さらにカーリーヘアのカツラをかぶるのだそうです。そして、モーリスと同じ広いオデコを表現するため、カーリーヘアの前方部をカットします。カットした端材で、もみあげを作れば完成。しかし、汗をかくと、もみあげの部分が剥がれてきてしまい、歌いながら動くと、走るダックスフンドの耳みたいにパタパタとなってしまうのだそうです。
さて、テレビのオーディション番組で、人気に火がついた「アース・ウインド&ファイターズ」は、数社からデビューの話があり、デビューが決まると、本格的に活動を開始します。その実力は、本家を上回るなどと言われるほどでした。今でも、「アース・ウインド&ファイターズ」と言えば業界で大変有名で、例えば、ボーカルの橋本仁さんは、「橋本仁」と紹介されるより、「ファイターズのボーカル」と紹介されると、「ああ、あの!」となるそうです。あるとき、活躍を続けるファイターズに、本家、アース・ウインド&ファイヤーのオープニング・アクトをやらないか、という大きな話が舞い込みました。しかし、残念ながらこの話は立ち消えになってしまいました。理由はわからないそうですが、ファイターズのビデオを観たモーリス・ホワイトさんが、仁さんのパタパタと羽ばたくカツラのもみあげを観て、「オレはこんなんじゃない」と不機嫌になった、ということがあったそうです。
 【2019年1月】 《大西ユカリ》
【2019年1月】 《大西ユカリ》
平成が終わろうとしています。平成の幕開けは私にとって印象深く、テレビ番組が特番ばかりになったり、学校が休みになったりと、世の移り変わりを感慨深く意識したことを覚えています。平成の二文字を国民に発表した当時の官房長官は、小渕恵三さんという方で、私の故郷の人でした。彼が緊張の面持ちで、マスコミのフラッシュを浴びるシーンは繰り返し報道されましたし、のちに総理大臣にもなりましたので、大変誇らしく思ったものです。
その平成元年には、ベルリンの壁が崩壊し、冷戦が終結。その後のソ連解体へと歴史が動きます。一方中国では天安門事件が発生しましたが、国が民主化運動の弾圧に成功したことで、共産主義崩壊までには至りませんでした。しかし中国はその後、資本主義経済を取り込んで大国になり、経済大国日本は中国に抜かれ、この平成の30年間で確実に衰退しました。裕福になった中国の人々が日本に旅行に来て、観光地はどこも中国人だらけ、という現象はもはや馴染みの光景ですね。
ところで、平成時代で一番記憶に残っていることといえば、私にとっては、オウム真理教の起こした大事件です。平成5年から7年くらいにかけての出来事なので、若い人はあまり知らないというから驚きですが、平和な国に起こった無差別テロ、未曾有の事件に対する連日の報道に釘付けになったものです。
事件が明るみになる前は、怪しい集団だと周囲で話題に上る程度でしたが、まさかあんな大きな事件を起こすなどは思いもよりませんでした。教祖がバラエティー番組に出たり、宗教学者で彼らの思想を肯定したものがいたりしましたし、信者たちも、異様な思想に染まってはいるけど、教義に一途なだけの善良な人のようにも映っていました。まだ犯罪の知られていなかったオウム真理教は、パソコン店や飲食店などの事業展開をして活動資金を調達していました。信者が無給与で働くわけですから、人件費が掛からないので、おそらく莫大な収入を得ていたことでしょう。そして我が高円寺の街にも、怪しげなグッズや、教団幹部のプロマイドなどを販売するオウムのショップがあったり、ラーメン屋があったりしたのです。
ラーメン屋は、高円寺純情商店街の突き当たりにありました。「うまかろう安かろう亭」という名の通り、ほんとうに安くて、店員も親切で、そこそこうまかったことを覚えています。通っていたころは、オウムのラーメン屋だとは夢にも思わず、後で知ってすごく驚きました。知らないって怖いことですね。 平成の次は、一体どんな時代になるのでしょうか。移民が増え、日本社会は大きく変わることでしょう。様々な思想、新しい考え方、異国の文化などが広まっていくことでしょうが、格差社会をほったらかしにして、歪んだ思想を生み出さないように気をつけなければいけません。あんな事件は二度とあってはいけませんから。
 【2018年12月】 《仙波清彦&カルガモーズ》
【2018年12月】 《仙波清彦&カルガモーズ》
腰痛に悩まされた一年でした。JIROKICHIの仕事は、基本立ち仕事だし、屈んで、ビール樽や機材など重いものを持ち上げる機会も多いので、出来ない時は、他のスタッフに迷惑をかけ通しでした。腰が悪いと、つい行動も緩慢になりがちだし、家でもなんとなく動かないようになってしまいます。寝起きも辛いし、靴下を履くのも一苦労です。出かけていて、駅の階段を踏み外したときなどは激痛が走ったりします。 これはまずい……いよいよ本腰を入れてなんとかしようと、ネットで検索し、高円寺で評判の良い整骨院を探しはじめました。幸いすぐに近所に良いところが見つかり、矯正、針、マッサージなど、様々な方法で治療をしてもらったのですが、劇的に良くなったのは最初だけ。あとは一進一退。なかなか完治しません。針を打ってもらった翌日は調子良かったり、打たなくても調子良かったり、治療の翌日なのに辛かったり。腰痛の治療に、時間がかかるのはわかるのですが、お金もかかるし、通い続けても治るという確信が持てず、どうしようかと悩んでいました。すると、ある日、YouTubeで、腰痛に関する驚きの動画を見つけました。とある有名健康番組の録画だったのですが、参考になるかと思って、何気なく観ていたのです。番組で語られた情報によると、腰痛になる人は「◯◯が良い人だ」といいます。果て、なんだろうと思っていると、びっくり。腰痛になる人は「寝相」の良い人だというのです。え? と思って続けて番組を観ていると、納得。人は、仰向けで、ほとんど動かず寝ていると、内臓と内臓脂肪の重みがモロに腰を圧迫し続けるのだそうです。やがて、重みで腰の筋肉が酸欠状態になり、身体が危険を知らせる反応を起こします。それが炎症という形で出るというわけです。これが慢性的な腰痛の正体でした。寝返りを打たない人は身体が硬い人が多く、また、マットレスがやわらかすぎたりする人もいるとのこと。自分は、たしかに、昔から身体が硬いし、布団の乱れ具合を思うと、あまり寝返りを打たない方かもしれないと思い、動画を観た日、さっそく仰向けにならないようにと意識して寝てみました。寝返りを打てていたかどうかはわかりませんが、その日、目が覚めてびっくり。全然痛くないんです。しばらく、この、仰向けで寝ないという方法を試しつつ、身体を柔らかくするストレッチをちゃんとやって、自然と寝返りを打てるようにしたいと思っています。テレビやネットの情報などあてにできないと思っていましたが、こういうこともあるんですね。
 【2018年11月】 《Chuck Rainey》
【2018年11月】 《Chuck Rainey》
少し前の話ですが、台風すごかったですね。今年は災害ばかりで、ニュースを見て気分が落ち込む日がずいぶん多かったように思います。先日の台風では、JIROKICHIに出演するミュージシャン御用達の立ち食いそばや「桂」さんが全壊してしまいました。ニュースで見てご存知の方もおられるかと思いますが、近所の私たちもとてもびっくりしました。「桂」さんはもう40年くらい営業しており、安くてうまいとファンも多いことから、心配の声がちらほら聞こえてきます。先日店主さんにお会いして状況をうかがったところ、なんとか年内には再開したいと言っておられました。以前、「桂」さんの「めかぶそば」が非常にうまいと、このコラムで取り上げたところ、読んでくれた方が食べにいってくれたらしく、それを聞いてなんだかうれしかった思い出もあります。少しでも再開のお役に立てるよう、募金を受け付けておりますので、もし余裕があれば何卒ご協力宜しくお願いします。
ところで今回、日本中を席巻した猛烈な台風24号は「チャーミー」という名だそうです。誰が名付けているかというと、日本を含む14カ国が加盟している台風委員会です。米国、カンボジアや北朝鮮、ベトナムなどが加盟していますが、各国が名前の候補を10個づつ提案・登録し、現在、全部で140の名前があるそうです。今回の台風「チャーミー」は、ベトナムがつけた名前で、花の名前だそうです。ちなみに、日本が登録した名前は、てんびん、やぎ、うさぎ、カジキ、かんむり、くじら、こぐま、コンパス、とかげ、はと。これらはすべて星座の名前だそうです。カジキ座とかコンパス座なんてあったんですね。もし年内に台風26号が発生すると、日本の順番がきて「うさぎ」になるそうです。台風「うさぎ」って、なんかかわいいですね。

「スパゲティ・ポヴェレッロ」というパスタをご存じですか。「貧乏人のパスタ」と呼ばれいるそうです。イタリアのレストランでもメニューに載っていないそうです。 茹で上げたパスタに、ニンニクの香りづけをし、目玉焼きをぐちゃぐちゃにして混ぜ合わせ、たっぷりの黒胡椒、おろしたチーズで仕上げただけの、シンプルなパスタです。料理の不得意な独身男性が、ビールでも飲みながらちゃっちゃと作る感じでしょうか。日本で言えば、卵かけご飯的な。しかし、これがたまらないというんです。JIROKICHIの営業後、よく行くバーの常連さんに、本も出している元イタリアンのシェフがいるのですが、その方に教えてもらいました。話を聞いて、早く食べたく食べたくて、翌日、さっそく作って食べてみました。盛り付けると、見栄えは良くありませんが、マジうまい。いわゆるB級グルメの類だと思いますが、すごく美味しいんです。これはクセになります。毎日食っても飽きない味かもしれません。皆さんも是非一度作って食べてみてください。チーズと黒胡椒、オリーブオイルはたっぷり入れると抜群です。 ところで飲み屋で、食べ物の話はいけませんね。お腹なんか空いていないのに、もう、たまらなくなります。常連客の中には、妙に料理の描写が上手な人がいたりして、そうなるともう、頭の中はその映像でいっぱいになってしまいます。 小説なんかでもそうですね。例えば、池波正太郎の「剣客商売」など読んでいると、主人公が、奥方や腕ききの料理人に作ってもらう献立の描写が毎度出てきて、またこれがいかにも美味そう。たまらなくなって、実際に作ってみたこともあるほどです。インスタなどで上手に撮られた映像で観るより、話を聞いたり、文章で味わったりした方がお腹が空いてくるのはどうしてでしょうか。 料理ってすごいですよね。食材に調味料を使い、火加減や、水加減、微妙な塩梅などを計り、器や、盛り付けにもこだわったりする。食事という生きるために欠かせない生命活動に対し、文化的な、複雑な楽しみ方ができるのは人間だけです。人間に生まれてよかったなと、つくづく思う食欲の秋、秋の夜長でした。
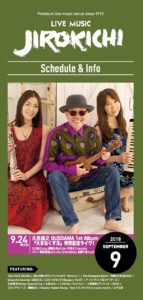 【2018年9月】 《久住昌之QUSDAMA 》
【2018年9月】 《久住昌之QUSDAMA 》
日本を代表するトロンボーン奏者、村田陽一さんにインタビューしました。
ジャズやクラシック、ポップスなどで幅広く活躍する、言わずと知れたトッププレイヤーですが、椎名林檎さんをはじめ、多くのアーティストにアレンジャーとしても信頼されている方です。 ところで、ジャズやクラシックを演奏するミュージシャンの多くは、両親の教育方針や、幼少の頃からピアノを習っているなど、ある程度のポテンシャルの高さがあるものですが、村田さんは、まったくそういう環境になかったそうです。たまたま入った吹奏楽部で、背が高いからという理由でトロンボーンをやることになりました。そのうち楽譜が読めるようになり、楽しくなって、やがて熱心になりました。楽譜の掲載された歌謡曲集を手に入れると、片っ端からメロディを吹いてみたそうです。中学生になると、もうプロになることを決め、そのための道筋を考えていたとか。 大学生になると、さっそくジャズメンとして活動をはじめました。同世代のジャズミュージシャンを集め、自分のバンドを結成。並行して、ホーンセクションの一員として参加していたロックバンドのメジャーデビューが決まるなど、順調に歩みました。ロックバンドでは、プロミュージシャンになることに反対するご両親を安心させるためという意識でテレビなどに出演していたとのことです。 村田さんの言葉で印象的だったのは、バンド活動、つまり自分の表現したいことをやる「場」についてでした。自分の音楽を作って発表することはせず、楽器一本でお金を稼ぐスタジオミュージシャンや、職人的なプロミュージシャンは、それはそれでいいけれど、自分はちがう、自分はやりたいことだけをやりたい。表現をしたい。その思いは、プロになって、依頼された数々の仕事をこなしながらも、一貫していたそうです。 職人ミュージシャンになると、依頼された仕事をこなすだけになります。自分の音楽を追求してみたくなって、いざバンドを組んでライブでもやろうかと思っても、もうできないのです。人脈を作っていないからメンバーを集められない、ライブハウスへの出演の仕方もわからない。つまり音楽の「場」の作り方がわからないのです。村田さんは、経済的事情などに流されることなく、ご自分の音楽を追求してきました。素晴らしい仲間をたくさん作り、常に生の「場」に自分を投げ入れていたんですね。そういう音楽に対する姿勢や経験が多くのアーティストに必要とされ、信頼されている理由の一つなのかもしれないと感じました。
 【2018年8月】 《鬼怒無月 》
【2018年8月】 《鬼怒無月 》
冷房に頼って寝ると翌朝だるくって一日中しんどいけれど、冷房をつけないで我慢すると睡眠不足になってしんどいし、どうすりゃいいんだ、という感じです。今年は熱中症で倒れる人が続出し、こまめに水分を摂るようにと毎日のように喧伝されています。 ところで、わたしは少年の頃、野球をやっていたのですが、昔は練習中、水を飲むことは絶対許されませんでした。今考えると、すごいことです。真夏の炎天下、過酷な練習で、汗は乾き、身体は塩を吹きます。意識が朦朧とするときもあったし、ボールに飛びついて倒れ込んだりしたら、簡単には起き上がれないような感じでした。でも、不思議と熱中症になるやつなんていなかったし、調子を崩して練習を休むやつもいませんでした。ちなみに、最近は、水分の摂りすぎはやっぱり良くないということになっているそうです。いったいどっちが正しいのでしょうね。 今と昔のカラダの関する知識の違いを考えると、面白いですね。わたしたちのころは、転んで怪我をすると、赤チンやマキロンという消毒液を塗られました。ところが今では全く使われないそうです。昨今は消毒液は良くないということに決まっているのだそうです。自然に備わった、患部を修復するための人体の機能をかえって遅らせてしまうからだそうです。ですから、ガーゼなどを患部にあてることもしないそうです。で、今ではどうするかというと、患部の泥や砂などを軽く洗い流すだけなんだそうです。 野球の話に戻ると、昔は、うさぎ跳びという、手を後ろに組み、しゃがんだ姿勢でぴょんぴょん跳ねて前進するという過酷な練習法があったのですが、私たちが卒業し練習から解放された頃、危険な運動ということで禁止になりました。実は膝に負担をかけるヤバい運動なのだそうです。しかし、わたしたちは、山のてっぺんにある神社の石段をうさぎ飛びで登らされたり、グラウンドを何周もさせられたりしましたが、別に膝を壊すものもいませんでした。(みんな、手を抜くのがうまかったのかもしれません笑) とにかく、わたしたちのころは、根性でなにもかもやり抜くという時代で、無駄な練習でもなんでもやってましたが、わたしたちのより後の世代になると、そういう考えは次第に廃れ、だから子どもたちはひ弱になったなどと、少し前はいわれたものですが、昔のスポーツ選手より、今の選手の方が格段にレベルが高いことを考えると、やはり昔の考えというのは、間違っていたんですね。きっと。

【2018年7月】 《峰さんと小島さん 》
安い酒を飲んで、悪酔いし、頭がズキズキ痛くなったという経験がある人は、きっと少なくないと思います。私も、若い頃、安いウイスキーを飲んで地獄のような悪酔いに苦しんだ記憶が多々あります。昨今のお酒は安い物でも品質がよく、味もいいので、悪酔いなどはしないことが多いのですが、例えば駅前の焼き鳥屋さんなどで、調子に乗って、安い酎ハイでも飲もうものなら、飲んでいる最中にもう頭が痛くなってきます。今は、一口飲めば、頭が痛くなるお酒を判断できるようになったので、滅多にそういう目にはあいませんが、やはり、安いお酒は安いというそれなりの理由があるようです。 しかし、安い値段でお酒を提供している飲み屋さんは、安いお酒を仕入れなければやっていけません。例えば、焼酎なら、甲類、乙類という分類があります。乙類の仕入れ値は、種類にもよりますが、甲類の倍以上しますので、それなりの値段で提供しなければ利益は出ません。 乙類はいわゆる本格焼酎というやつで、芋焼酎、麦焼酎など、原材料そのものの香りが残る、味わい深い焼酎です。単式蒸留といって、一度だけ蒸留してアルコールを取り出します。ですから原材料の風味が多分に残るというわけです。甲類は、連続蒸留式という製法で、主に廃糖蜜といって、サトウキビから砂糖を作り出す工程で残ったタール状の廃棄物(と言っても有害なものではありません。ラム酒、味の素などもこれらを原料にしています)を発酵させて造ります。発酵したアルコール分を熱し、何度も蒸留することで、純度の高いアルコールのみを取り出し、水で薄め、精製して製品にしています。ですから甲類の焼酎の場合、原材料はあまり関係ないのです。穀物や果実など糖質が含まれていればどんな原材料でも造れるそうです。 居酒屋さんなどで飲む安い酎ハイは、この甲類という焼酎を使います。一斗缶などで超安く仕入れて客に提供しています。何度も蒸留するので、無色透明になり、癖のない、割りものに適したスッキリとした味になります。甲類の方がカロリーもないし、悪酔いしなくて、好きだという人も多いようです。 しかし、この蒸留の過程に手を抜くと、メチルアルコールなどの不純物が残ってしまうことになります。味も香りも良くありません。そこで、添加物を使って味を調整することになります。この不純物や添加物が頭の痛くなる原因だとか。蒸留酒にしても醸造酒にしても、あまりにも安いお酒には、不純物や添加物が入っていると考えて良さそうです。しかし、焼酎についていえば、値段の安い甲類焼酎といっても、体内のアルコール分解は乙類や醸造酒よりも早いそうですから、二日酔い、悪酔いの本当は、単なる飲み過ぎということなのかもしれませんね。ちなみにジロキチの焼酎はすべて乙類です。甲類が苦手な方はご安心ください。

くすんできた店の外観をキレイにしようと、スタッフ総出でペンキを塗りました。普段、地下の陽の当たらないところで仕事をしていますから、昼間の陽光や風が大変心地よく、楽しく作業できました。JIROKICHIは基本、なんでも自分たちで作ったり直したりするので、かなり慣れていますが、やはり、プロとは雲泥の差で、かなり時間がかかってしまいます。 夕方、ようやく作業を終えて、さあ、打ち上げ。大仕事の後に飲むビールが美味いことは言うまでもありません。 ところでビールって、いつから美味しいと感じるようになったのでしょう。父親があまりにも美味しそうに飲むので、少し口をつけてみたら、ひどく苦い……こんな経験のある方も多いかと思います。とにかくビールが美味しいと感じるようになったら大人なんだそうです。大人になると苦味の良さがわかるようになってきます。人間はストレスを受けると、苦味を感じる味覚のレセプターが鈍くなるそうで、そういう理由もあるそうです。 日本でビールが飲まれるようになったのは、明治時代ですが、ビールの歴史はすごく古いというのを知っていますか。石器時代まで遡るといいます。貯蔵していた麦が発芽してしまい、しかたなく粥にして食べたところ、甘くて美味しかったというのが最初のようです。文明が起こったころには、もう飲まれていました。古代エジプトのピラミッドを建設していた作業員たちの現場から、ビール製造所の跡地が発見され、製造の様子を描いた壁画や、製造方法を歌った讃美歌なども残っているそうです。古代エジプトではファラオから庶民まで一般的によく飲まれていました。酔っ払ってストレス発散、というだけではなく、栄養源としても重要だったようです。重い石を高く積み上げる作業は相当過酷だったかと思いますが、仕事の後の一杯はさぞ美味しかったことでしょう。こんな話を書いていたらビールが飲みたくなってきました。ちなみにJIROKICHIの生ビールはサッポロ黒ラベル。ビール通はサッポロが好きなんです。

【2018年5月】 《冨田麗香&ザ・ローリングジプシーズ》
散歩するにはいい季節になって、喜ばしい限りです。ところで、桜の咲き始めのころ、ソメイヨシノの発祥の地である駒込を経由して、巣鴨のとげぬき地蔵に行ったのですが、巣鴨って最高ですね。巣鴨の地蔵通り商店街は、「お年寄りの原宿」などといわれていますが、たしかに年配の方が多く、昔ながらの商店街がそっくり残っていて、いい感じで賑わっていました。なんとなく時間がゆっくりと流れているような気がして、とても気分がいいのです。原宿でクレープを食べ歩きするみたいに、大学イモ、焼き鳥などを片手にのんびり歩いていると、ふと、シブいお茶屋さんを見つけました。入ってみると、店を任されているのはインド人の若者です。注文すると、彼が丁寧にお茶を点ててくれたわけですが、これがちゃんとしていて、非常に美味しい。いろいろ訊いてみると、静岡で、師匠についてお茶を本格的に学んだとのこと。日本に来た理由は、大学で経済学部に学ぶためだったのですが、お茶の魅力に取り憑かれてしまい、とうとう師匠から店を任されるようにまでなったのだそうです。 「日本は少子高齢化で、働き手がなくなってます。外国人をどんどん受け入れて経済成長を維持しなければならないでしょう」 日本人の心を私よりもわかっている上に、痛いところを突かれ、日本の抱える最大の問題について、意見までされてしまう始末です。まいったな、と思いながら、再び地蔵通りに復帰すると、今度はいい感じのタコ焼き屋さんを見つけました。店内は結構広く、お酒も飲めるようです。メニューを見ると、タコ焼きのほか、明石焼きや、おつまみなども充実しているようなので、思わず入ってしまいました。 びっくりしました。タコ焼きはもちろん、明石焼きも、出汁が効いていて非常に美味しいし、サービス満点。しかし、店員さんは全員インド人。よく見ると、タンドリーチキンまでメニューにあります。かつて、日本のインドと言われた高円寺ですが、私はなんとなく負けたような気になって高円寺に帰ってきました。
 【2018年4月】 《こまっちゃクレズマ》
【2018年4月】 《こまっちゃクレズマ》
「肉じゃが」が好きです。肉じゃがといえば、肉、じゃがいも、人参、玉ねぎ、が基本で、煮崩れしにくいとのことでしらたきを入れたり、別茹でのさやえんどうなどを添えたりする場合もあります。個人的に、肉じゃがに使う肉は豚バラが一番うまいと思っているのですが、大阪出身の人が「肉じゃがの肉は牛肉が普通だ」というのを聞いて大変びっくりしたのを思いだします。ところで肉じゃがは、和食だと考えられていますよね。まあ、日本でしか食されていない料理ですから、和食なんだとは思いますが、実はこの料理、明治時代に日本の料理人がビーフシチューを再現しようとした結果出来上がったものなのです。ヨーロッパ視察に行ったあるお偉いさんが、向こうで味わったビーフシチューの味が忘れられなく、知己の料理人に再現を頼みました。見たことも、食べて味わったこともない料理ですから、料理人の方は大変苦労したと思いますが、工夫に工夫を重ね、なんとかそれ風の料理を作りあげました。こうして誕生したのか「肉じゃが」です。ちなみに肉じゃがはお酒のつまみとしても最高です。 ところで、ハンバーグも大好きです。ハンバーグはハンブルグ・ステーキのことですから、ドイツのハンブルグで生まれた料理かと思いきや、実はモンゴル出身です。時代は遡って、チンギス・ハンのモンゴル帝国の時代です。モンゴル帝国はヨーロッパにまで影響力を及ばせ、ヨーロッパの人たちはモンゴル人をタルタル人と呼んで恐れたそうです。モンゴル人は、ビタミンを採るために馬肉などを生で食べました。しかし、馬肉はスジが多く、非常に硬いため、細かく刻んで食べていました。それが、後のタルタル・ステーキです。ヨーロッパにもたらされたタルタル・ステーキは、あるとき、鉄板で焼かれ、ドイツのハンブルグで評判になりました。こうしてハンバーグは生まれました。
ちなみにタルタル・ステーキは日本には伝わりませんでしたが、韓国には伝わりました。そうです、焼肉の定番メニューの一つ、ユッケです。ついでに、韓国といえばキムチ。キムチは唐辛子をたくさん入れて漬け込みますが、唐辛子は、実は日本から韓国に伝わったものです。豊臣秀吉が天下を取り、晩年、明(今の中国)を攻めたときのことです。秀吉の命令で朝鮮に渡った武士たちは寒さをしのぐ為、カイロの代わりに唐辛子を持って行きました。キムチの歴史は案外古くないんですね。食文化の歴史は調べてみると面白いものです。
「仮想通貨」ってご存知でしょうか。ハッキングされて580億円分が大量流出した、などのニュースを見てなんとなく知っている方も多いと思います。しかし通貨っていうけど、お金なのか何なのかよくわからないという人のほうが多いのではないでしょうか。
「仮想通貨」は「暗号通貨」ともいわれ、インターネット上にデータとして存在する通貨です。つまり紙幣や硬貨など、手で触れることのできる通貨とは違い、まさに「仮想」の通貨です。 仮想通貨は何種類も存在しますが、「ビットコイン」が最も有名です。ビットコインはしばしば「金(ゴールド)」に例えられます。地球上で採掘されつくした「金」と性質がよく似ていて絶対量が定められています。投資家は、円やドルなど法定通貨で仮想通貨を買ってインターネット上に保有し、相場を見極め、売買しています。 ビットコインは現在、1BT=100万円くらいで取引されています。2010年に最初のビットコインが生まれたときは(金のように掘り出されたときは)1BT=0.006円だったそうですから、たった8年で、信じられない値上がりをしたわけです。ですから、早くから注目してビットコインを買っていた人はみんな億万長者になりました。それでにわかに注目を集めたわけです。 ビットコインは、国がお墨付きを与えた通貨でもないのに、なぜこれほど価値が上がったのでしょうか。ビットコインはいってしまえばアイドルの限定サイン付きCDみたいなものです。本気のファンであれば手に入れたいレアなものでしょうが、興味のない人にとってはゴミ同然です。ところがそのアイドルは、まだ眠っている魅力がたくさんあり、歌もうまい、演技もうまい、スター性も抜群だと知れ渡り、いずれ国民的エンタテイナーになるだろうと見込まれたわけです。それで希少価値が出て限定サイン付きCDの値段が定価より上がったので、売り手が現れ、買い手が生まれたというわけです。
ところでアイドルの限定サイン付きCDは、そのアイドル自体に大変魅力があるわけですから、とにかく価値があるとわかります。しかし、仮想通貨はなにがその「魅力」なのでしょうか。それは「ブロックチェーン」と呼ばれる新しい技術です。ブロックチェーンについて説明しだすと長くなるので割愛しますが、現在の社会の仕組みを根底から変えると言われている革新的なアイデアです。仮想通貨はブロックチェーンという技術によって運営されているため、将来、円やドルに変わる世界的な通貨となるかもしれないと期待されました。しかし、やはり、難しいようです。ブロックチェーン技術自体は、様々な公共サービスに応用される可能性を秘めた素晴らしいものですが、仮想通貨は今のところやっぱり「仮想」です。公共サービスに使えたり、世界共通の通貨として世界中で買い物できるようになったりしなければやがて消えていくことでしょう。アイドルもアイドルから脱皮できなければ、人気が衰え、消えていくのと一緒ですね。

【2018年2月】 《有山岸》
昨今の電化製品や道具類は、すぐに壊れたりしてよく買い換えたりするものですが、昔の製品は、なんでもずいぶん長持ちするような気がします。JIROKICHIは相当昔から使い続けている機材や道具が多いのですが、一番驚くのは、ステージでミュージシャンのモニター用に使っているBOSEというスピーカーです。これは全然壊れません。なんと40年近くも使っています。他には、ギターアンプ「JC120」。これも非常に丈夫で、25年くらい前に中古で買って日々酷使しているのにも関わらず、あまり壊れることなく助かっています。エンジニアのワオさんが自作したDIという機材。これも全然壊れません。しかもいい音で、未だに現役で活躍しています。 YAMAHAの人がわざわざ見学に来たことがあるというドラムセット、YAMAHA/YD900Rも、ジャズドラマー村上寛さんに譲っていただいてからずっと40年以上使っています。このドラムセットは、今では手に入らない木材を使って製作された名器で、ドラマーの方々にファンも多く、毎日のように使われています。店の音に馴染んでいることもあり、買い換えるつもりは毛頭ありませんが、しかし壊れて使えなくなるようなことは当分なさそうです。その他、厨房のフライパンや、油鍋、小道具類などにも、40年以上使っているものがたくさんあります。古いし、別に買い換えてもいいのですが、なんとなく愛着があってそういう気にならないのです。 資本主義社会においては、モノはどんどん使い捨ててバンバン買い換える方が、お金がまわって、景気も良くなり、税収も上がって、みんなが豊かになる仕組みなのですが、そんな社会システムに抗って…… というわけではないのですが、修理して何十年も使っている機材や道具をなんとなく良いモノのように思って使い続けています。モノを粗末に扱うな、もったいない、まだ使えるから取っておけ、などと昔はよく言ったものですが、今は、断捨離などといって、まだ使えるものでも、まだ着れる服でも、どんどん捨てられる世の中です。豊かになってモノが溢れているのに、商品に新しい付加価値を無理やり与え、大量にモノを生産し続けなければ破綻してしまう社会ですから仕方がありません。かといって、資本主義から脱却し、不便だった時代に戻ることはできそうもありません。共産主義、社会主義的な考えを安易に述べる人もいますが、それがうまくいかないことは歴史が証明していますし、もっと極端に、例えば原始時代のような生活に身を置くことなど絶対に不可能でしょう。 しかし、どうしても、昔からずっと使っている古いモノには特別な「なにか」が宿って、新しいモノより優れた価値があるような気がしてしまうのです。きっとブルースなど古い音楽が好きなのも、そういう性分のせいなのかもしれませんね。

【2018年1月】 《ハモニカクリームズ》
2018年。私が子供のころには想像もできなかった未来です。社会は大きく変わりました。人々はコミュニケーションの手段をインターネット、スマホにシフトし、思想、音楽など、文化の発展も頭打ちになったように見えます。今後、近未来においては、人工知能、アンドロイド、ロボットなど新しい技術の一般化によって社会はさらに大変革することでしょう。一人一台ロボットを所有する、SFのような世界が本当に実現するそうです。そうなれば人々はもう他人とは関わらなくなります。すでに若い人たちは恋愛さえも敬遠する傾向だそうですから、例えば、バンドなど面倒な人間関係を必要とする集まりはもうなくなってしまうのかもしれません。 キーボーディストの加藤エレナさんにインタビューしたとき、JIROKICHIのオープン当初から出演していただいているようなレジェンド的ベテランの方々と共演する際の話になりました。昔のバンドマンたちはとにかく人間関係の密度が濃い時代を生きてきたのです。理由の一つに当時の情報の少なさがあります。今のようにネットはありません。バンドをやろうとなれば、レコードを持っている人など情報を多く持つ人と友だちにならなければならないし、楽器を手に入れて楽曲のコピーをするにしても、演奏技術を教えてもらったり、逆に教えたり、朝まで酒を飲みながらああでもないこうでもないと音楽について議論したり、とにかく始終顔を付き合わせて過ごしたわけです。そうやってずっと一緒に過ごすうちにバンドごとの個性豊かな独特の雰囲気を作りだしていったわけです。 最近の若いバンドは……などとエラソーにいうつもりはありません。酒が飲めなくったっていいし、必要事項だけをメールでやりとりしていれば、効率だってはるかにいいし、演奏することにおいては問題ないはずです。もしかして将来、わざわざリハーサルスタジオに行って練習をしなくても、ネットを通じてそれぞれの自宅にいながら十分にリハができるようになるかもしれません。 面倒なコミュニケーションがいらなくなる時代。けれどそうなったら人間の演奏を聴いていてもどこかロボットの演奏を聴いているようで、ライブを聴く感動はなくなってしまうことでしょう。